西岡智(西岡兄妹)
|

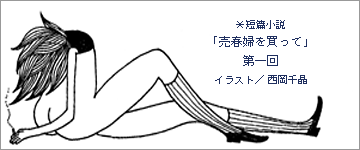 |

売春婦を買って街を歩いた。「買った」というよりは「拾った」という感じ。平日の午前、夜の仕事の人たちは家路につき、通勤ラッシュも終わった頃、中途半端に人がまばらなそんな時間、ぼくは一人歓楽街へ向かっていた。まだシャッターの下りている店の前で足を投げ出して座っている女。まるで昨日の夜からそのままの形で置かれている人形のように身動きさえしない。世の中にはなぜだか分からない、何と言っていいのかも分からない、ただ「途方に暮れた」感じを抱いて生きている人種がいる。ぼくもそうだった。ぼくと同じ空気感をその女に感じて足が止まった。同種の人間だけがもつ妙な親近感。そこだけぼんやりとした時間が流れ、人目も気にせずぼくは女に近づく。ダメージジーンズというのだろう、破れ目から見える膝が白く艶めかしい。ひとつ息をついて女に声をかける。
「いくつ」
「二十歳」
「いくら」
「二万円」
それだけだった。
奇妙な朝だった。精神のバランスを崩し病院にかかるようになった頃から、性欲というものをぼくは完全に失っていた。食欲もないし夜も眠れない。「あなたからは生体がもつエネルギーといったものが感じられない」医者にはそう言われていた。ちゃんとした病名もなくただ睡眠薬だけ処方されていた。勃起しないペニス。男として絶望的な事実であるはずなのに、なぜか他人事のような無関心さで、自分の現実に接していた。
遅い朝、目を覚ますと腰のあたりに奇妙なしびれのようなものを感じた。微かではあるが勃起しているのだ。いや勃起というのとは違う、じわりとした感覚を伴ってペニスが少し膨らんでいる、そんな感じ。頭は普通に冷めているのに、下半身だけに感じる焦燥感のような感覚。性欲というより排泄感に近い。勃起時特有の切れの悪い小便をする。左右に飛び散り便所を汚した。小便をしてもその感覚は消えなかった。今まで感じたことのない奇妙な性欲。そう、性欲には違いないのだ。とにかく「出した」かった。部屋で一人ですることに抵抗を感じた。とても惨めな気持ちになるような気がした。女が欲しかった。女の中で出したい、そう思った。ソープランドに行こう、ぼくは金をポケットに突っ込んで部屋を出た。
女はホテル街とは反対の方向に歩いて行く。2、3歩あとをついて歩く。
「ホテルに行こうよ」
「そんな、もったいない」
振り返って女が笑った。これから売春行為が行われるというのに、女の足取りは妙に弾んでいる。布製の花柄のバッグが上下に揺れる。
営業マンたちが下げたくもない頭を下げ、中年の女たちが本当は無目的な買い物のためにデパートで物色を始めるそんな時間。ぼくはこれからセックスをする女と一緒に街を歩いているのだ。優越感にも似た不思議な感じを抱きながら、女の後をついて歩いた。
駅に着いた。女が2枚切符を買ってくる。どうやら自分の部屋に連れて行こうとしているようだ。一瞬不安を感じたが、それもすぐに消えた。同種の人間が持つ理由のない安心感、女もぼくに対して同じ感じを抱いているように思えた。
JRから乗ったことのない私鉄に乗り換える。この時間、下りの電車だというのに車内は意外と込み合っていた。女はドアにもたれて立っている。吊り革を持ったぼくの脇の下あたりに女の顔がある。意外に小柄なんだなと思った。ここにきて初めて女をしげしげと見つめた。痩せているというより骨が細いのだろう華奢な体つき。二十歳と言っていたがどうみても16歳くらいにしか見えない。血管が浮き出て見えるほど薄く白い肌。瞳が微かに茶色く、背中まで無造作にのびた髪と同じ色をしている。大きな眼球と、それに比して極端に薄い目蓋。そのせいか目にまったく表情が感じられない。何だか爬虫類っぽい感じ。かといって決して醜いという訳ではない。どちらかといえば美人の部類に入るだろう。腰のしびれ感が強くなってくる。手を触れれば今にも漏れ出してしまいそうだった。
電車はゆっくりと住宅街の中を抜けて行く。線路と家々の距離が近い。同じような風景が延々と車窓を横切って行く。駅に着く度に乗客が降りていくが誰一人乗ってこない。座席は空いてきたが、ぼくたちはドア付近に立ったまま電車に揺られていた。
「手をつなぎましょうか」
ポケットに入れていたぼくの左手を引っ張りだし指を絡めてくる。
「これラブつなぎって言うのよ」
そう言って小さく声を立てて笑った。
知らない駅で降りた。どこにでもあるような住宅地。ぼくたちは手をつないで歩いた。やけに坂が多い。息が切れる。いつになったらできるのだろう。ぼくの「性欲」は限界に近い。女が急に足を止めた。住宅地には不釣り合いの奇妙な建物だった。三階建てのアパートくらいの高さはあるだろうか、窓のない四角いコンクリートの固まり。中央に鉄製のドアが一つ。女がドアを開ける。きいとドアがきしんだ。中に入る。手すりをつたって短い階段を下りる。打ちっぱなしのコンクリートの半地下のガレージのような場所。裸電球が一つ吊るされて薄暗い。大きな換気扇がかたかたと音を立ててゆっくり回っている。煙と湯気が喉を突いてむせた。5、6人の浮浪者然とした男たちが料理をしたり酒を飲んだりしている。何が何だかさっぱり分からない。料理の臭いに混じって小便の臭いが鼻を突いた。男たちの視線が一斉にぼくに向かった。皆ニヤニヤと嫌らしい笑いを浮かべている。女はぼくの手を引いて男たちの間を抜けていく。不意にワンカップ酒のコップがぼくの足下に飛んできて音を立てて砕けた。驚いて声を上げてしまう。男たちがどっと笑った。
「気にしなくていいよ、からかってるだけだから」
女がそう言ってぼくの手を強く握った。
鉄製の梯子が天井に向かってのびている。先には天井に張り付くようにしてドアがあった。見ると他にも同じようなドアが天井に並んでいる。こんな建物は見たことも聞いたこともない。訝しがっているぼくをよそに女は梯子を上っていく。他にどうしようもない。今頼りになるのはこの素性も知らぬ女だけなのだ。ぼくもあとについて上った。女がドアを開ける。鍵はかかっていなかった。続いて部屋に入る。女が内側から鍵をかける。真っ暗な中、手探りで裸電球をつける。手慣れたものだった。
6畳ほどの広さ。窓がないことと床にドアがあること、そしてこの肌に粘り着くような湿気を除けば、古いアパートとそうは変わりがない。思ったよりこぎれいに整理されている。でもどう見ても若い女の部屋には見えない。部屋の中央に敷きっぱなしの布団。最低限の生活用品はあるようだが、まったく生活感がしない。
「君の部屋なの」
女は首を横に振った。
「たまに借りているの。でも大丈夫、誰も帰ってこないから」
売春用に誰かから借りているのだろうか、状況の理解がまるでできない。もう少し話したいというぼくの思いを遮るように、女が服を脱ぎ始めた。とにかく早く終わらせてしまいたい、そう言っているように思えた。それはぼくも同じだった。詮索してもしょうがないことだ。目的さえ果たしてしまえば、こんなところにもう用はないのだし、この女と会うこともたぶんもうないのだから。
女が裸になる。ぼくに背を向け、バッグの中から何やらローションのようなものを取り出して陰部に塗っている。やっぱりプロの売春婦なんだ、なぜか少し寂しい気持ちになる。裸になると女の体は想像していた以上に細い。腰の曲線がなければまるで小学生のようだ。女が布団に仰向けになって足を広げた。ぼくも急いで服を脱ぐ。裸になって女の足の間に座る。水がしみ出てくるかと思えるくらい湿った布団。
起たない。まったく起たないのだ。何とかしようと手でこすった。でもぴくりとも動かない。あれほど強かった「性欲」がただの焦燥感に変わっていくのを感じていた。
「口でしてくれないか」
女の顔の方に回ってそう言った。その瞬間、女が否と顔をそむけた。まるで芋虫を握り潰すような感触。何の快感もなく大量の精液が指の間から漏れだして、女の髪を汚した。
「ごめん」
なぜだか分からない、急に涙があふれてきた。決して悲しい訳ではないのに、もう何年も泣いたことのない目から、涙があふれて止まらなかった。女は怒るでもなく、慰めるでもなく、黙々と髪の毛をティッシュペーパーで拭いている。とにかくここを立ち去りたい、もうそれだけだった。
泣きながら下着をはこうと立ち上がったその時、ノックの音が。女の顔が急に引きつって、飛び跳ねるようにして部屋の隅で丸まった。怯えた表情、見るだけで体が震えているのが分かる。ノックの音が大きくなる。部屋の持ち主が帰ってきたのだろうか。女は声もかけられないほどに怯えている。ドアが壊れるのではないかと思えるほどのノックの音。ぼくは泣きながら精液で右手を汚したまま、途方に暮れて、裸で布団の上に立っている。地面から突き上げるようなノックの音が。
|
| おわり |
|
|

| 西岡兄妹情報 |
|
小説は初心者なので、長い目で見てやって下さい。
(西岡智) |
|