西岡智(西岡兄妹)
|

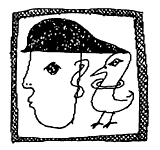 |
*短篇小説
「寝言」
第三回
イラスト/ 西岡千晶 |
|
|

|
寝言
ぼくのアパートの隣りの部屋には、ここ数年誰も住んでいない。それもそうだろう、こんな広いだけが取り得の、老朽化してそこいら中にがたがきているアパートに、今時の人がわざわざ引っ越してくるとは思えない。エアコンすら付いていないのだ。年々、歯が抜け落ちるように人がいなくなる。金がなくて引っ越しのできない連中が、大家の惰性にただぶら下がっているような、そんなアパートなのだ。ぼくの部屋は東側の二階の角部屋で、お隣さんといえばその部屋だけであって、まあ、騒音だ何だと気を遣う必要もなく、気楽といえば気楽ではあるが、隣りに誰もいない何もない空間がぽかりと空いていることを想像すると、少々薄ら寒い気がしないでもなかった。
しかし、どのくらいだろう、数ヶ月ほど前から、夜になると誰もいないはずのその部屋に、人の気配が感じられるようになった。声がするわけではない。これといって物音がするわけでもないのだが、誰かがいるような気がしてならない。最初は管理会社の人間かとも思って気にもとめないでいたのだが、それが週に一度、三日、二日に一度になってくると、やはり気になるものだ。水道や電気のパンフレットはドアノブに掛けられたままで、誰かが引っ越して来たという様子もない。隣りは隣りと気にかけないようにつとめてはみるが、やはり薄気味悪い。でも明日も仕事なのだ、朝は早い。ぼくは処方されている睡眠薬を飲んで、落ちるように眠っていた。
夜11時くらいだったろう。またあの気配がしたので外に出て隣りの様子をうかがった。電気は消えているし、鍵もかかっている。不思議なことに外からではあの気配がまるで感じられない。さすがにノックまではしなかった。でも部屋に戻るとやはり確かに隣りに誰かがいるのだ、音も立てず、じっと息を殺して。
管理会社に確認してもらおうとも思ったがやめた。配管の水漏れでさえうるさく言わないと直してくれない大家が、こんなはっきりとしないことに金を使ってくれるとは思えなかった。下手をすればぼくが異常者扱いされかねない。こんなアパートには、少し線の切れた人間が一人はいるものだ。そんな立場になりたくはなかった。大家は知らないことだが、ぼくが精神科にかかっていることも、二の足を踏ませる一因だった。
日に日にぼくは追いつめられていった。睡眠薬を飲んでも熟睡できなくなっていった。テレビをつけたまま、部屋の灯りもつけたままで、少しでもあの気配をかき消そうと、でもそれを確実に感じながら、悪夢とも現実とも分からぬ浅い眠りを漂って、明け方眠りに落ちたと思った瞬間、目覚ましが不快な朝を知らせた。そんな日が続くようになった。さすがに仕事にも支障がでるようになって、何の期待もなかったが精神科医に相談した。
「よくないですね、幻聴というやつです。まあ、あなたのような方の場合よくあることですが。お薬を少し増やしましょう、それで様子を見て下さい」
思っていた通りの反応。安定剤と睡眠薬が少し増やされてそれで終り。
薬を飲むのをやめた.医者に対する反感もあったのかもしれない。世間ではただの幻聴、幻覚でしかないかもしれないが、ぼくにとっては明らかな現実なのだ。やつは、あの男は
―なぜだかぼくはやつが男だと決めつけていた― 確実にそこにいる。壁一枚隔てた向こうで、音一つたてず、ぼくの様子をうかがっているのだ。漠然とした不安は確信へと変わっていた。何らかの悪意をもって、少なくとも何かの目的をもって。
薬をやめたからだろうか、ぼくの神経は過敏になっていた。少しの物音に身震いするようになった。夜は全く眠れず、昼間に浅い眠りをとった.当然のこと、仕事も何やら理由をつけて休んでいた。ぼくは心も身体も憔悴しきっていた。理由は分からない、なぜか突然やつは現れなくなった。もう目的を果たしてしまったのだろうか、それともぼくが夜目を覚ましていることに気づいて、用心しているのだろうか。不思議なことにぼくはどこかでやつが現れることを期待していた。ぼくの生活の中でやつだけが、あの男だけが唯一の目的のようなものに変わっていった。どうするつもりなのか、ぼくは何がしたいのか、それは分からなかった。そんな夜が二週間ほど続いた。
ある夜、真夜中に不意にやつは現れた。鍵を開ける音が微かに聞こえた。鍵を閉める。神経過敏のせいだろうか、それまで気配としてしか感じられなかったやつの行動が、まるで手に取るように分かった。やつはすり足で壁際に近づくと、座り込んで耳をぴたりと壁に当てた。そのまま何時間も身動き一つせず、そうしていた。やはりそうだったのだ、やつはこうしてぼくの部屋の様子をずっとうかがっていたのだ。ぼくの確信は間違ってはいなかった。
どのくらいたっただろう、急にやつが立ち上がった。そして今度は明らかに足音が聞こえるくらいの早足で玄関に向かった。何を思っていたのだろう、ぼくも跳ね上がるようにしてやつの後を追った。やつがドアを開ける、ドアを閉める。ばたばたと何だかやけに慌てている様子だ。ぼくがドアを開けると、黒い陰が階段を駆け下りていくのが見えた。二、三十メートル走っただろうか、その黒い陰が少し歩調を緩めた。観念したのかもしれない。ぼくは一定の距離を保ちながらやつの後をついて歩いた。捕まえようと思ったら捕まえることはできたかもしれない。でもそうしなかった。知りたかった、何をと問われてもきっと答えることはできなかったろうけれども。
夜はまだ明ける様子さえ見せなかった。湿った濃い灰色が家々にへばりついていた。ぼくはやつの黒い陰を追って、やや早足で歩いていた。湿気の多い不快な夜だ。腋の下で汗が粘り着いた。街路灯のない、中小の工場の建ち並ぶ風景の中にぼくは足を踏み入れていた。ぼくに後をつけられていることは知っているはずなのに、やつは歩調も変えず、まこうという気配も見せず、淡々と歩を進めていた。入り組んだ路地をいくつか曲がる。うら寂れた今時トタンで壁を打っているようなアパートが見えた。その一室の前でやつが止まった。鍵を開ける。ぼくは駆け出してやつの肩を掴んだ。細い肩が一瞬上下した。やつが振り返った。
小柄で華奢な体つき、不自然なほどのなで肩から細く長い首が伸びて、その上に大きな頭が乗っかっている。いかにもバランスの悪いひ弱そうな体型。ぼくが手で突いたら崩れてしまいそうに弱々しい。中学生のような髪型、離れた両目が小さな鼻といびつな三角形をつくっている。薄い唇が左右に顔を引きつらせ、一見して蛙のような印象。左の口角がわずかに上に上がって笑っているようにも見える。人に対して何の恐怖も脅威も与えないが、何とも言えない苛立ちを感じさせる容貌。
「どういうことか説明してもらおうか」
少し語気を強めて言った。何を言っていいのか分からなかった。
「こんな所では何ですから中にお入りになりませんか、まあ、お茶も出せませんが」
トーンの高い、かすれた抑揚のない声で男が言う。
男の後について部屋に入る。男が灯りをつけると一瞬身じろいだ。そこはアパートの一室というよりどこかの会社の資料室のようだった。スチールの本棚が窓までふさいで、ファイルされた資料が、ぎっしりと詰め込まれている。入りきらないファイルや紙切れが床に散乱して、部屋の中央にはパソコンが一台無造作に置かれている。
「まあ、お座り下さいと言いたいところですが、見ての通り座る場所もない」
しぇっしぇっと空気が抜けるような音をたてて男が笑った。無性に腹が立った。
「怒らないで下さい、こう見えて小心者なんですから。まあ、お腹立ちは分かります。大変な思いをされたようですからね」
「他人事じゃないだろう」
自分でも驚くくらいの大声で怒鳴った。
「大きな声を出さないで下さい、お願いですから。小心者だと言ったじゃありませんか」
笑っているような顔が気にはなったが、確かに怯えている風は感じられた。
「とうとうこんなことになってしまいました。決してわたしが望んだことではなかったのですが。あなたは特殊なケースなのです。普通の方はわたしのことで思い悩んだりはされません。それどころかわたしの存在すら気づかない場合がほとんどです。あなたもわたしになど気づかなければ何の問題もなかったのです。気づきさえしなければ、わたしなど存在しないのと同じなのですから。でもあなたは気づいてしまわれた。そして苦しまれたあげくに、こうしてわたしを追いつめてしまわれた。これはわたしの望むところではありません。そしてあなたにとっても決して幸せなこととは言えません。残念です」
「ぼくはお前がなぜぼくの隣りの部屋で何を…」
舌がもつれて言葉が途切れた。
「あなたはわたしがあなたの隣りの部屋で何を目的として何をしていたのかをお知りになりたい。そういうことですね。それは当然の要求です。が、知るということがいつもその人のためになるとは限らないということもあります」
「いいから教えろ」
男の襟元を掴んだ。男の身体はまるで抵抗ということを知らないかのように軽々と左右に揺れた。
「寝言です」
「寝言?」
「そうです、寝言です。びっくりされましたか、それともがっかりされましたか。わたしはあなたの寝言を聞いていたのです。いや調べていたといったほうがいいかもしれませんが。それだけなのです。あなただけではありません。ずいぶんたくさんの人の寝言をこれまで調べてまいりました。あなたはその一ケースに過ぎません。まあ、確かに興味深いケースではありましたが」
「変わった趣味もあるもんだな」
「趣味と言いますか、仕事と言いますか」
男が自嘲気味に笑みを浮かべた。
「で、どうして、なぜそんなことをしているんだ」
「それはお話しすることはできません。正直わたしにも何と言っていいものやら分からないのです。こうなってしまった以上、嘘も隠し立てもいたしません。でも本当にそれはわたしの口からはお話しすることができないのです。ご容赦ください」
嘘を言っているようには聞こえなかった。一種の変質者、それくらいに理解するより他なかった。
「お前はぼくのことを、興味深いケースだと言ったな。ぼくが寝言で何を言っていたのか、どこがどう興味深いのか教えてもらおうか」
なぜか分からない。急に抗いがたい衝動に襲われた。ぼくはぼくの寝言が聞きたくなった。
「それはお勧めできません」
何も言わず男の肩を強く突いた。やはり男は何の抵抗もなくふわりと浮いて、そして変な関節の曲がり方をしてぐにゃりと倒れ込んだ。立ち上がった男の身体は恐怖のために小刻みに震えていた。
「本当に小心者だな。こんな男のためにぼくは…」
男が一冊のファイルをぼくに手渡した。ファイルを開けた。そこには暗号やら記号やらわけの分からない文字とも呼べないようなものが並んでいて全く読めない。
「これはわたしにしか読めないようになっているのです。なにしろみなさんの大切な秘密ですから」
震えた声で男が言った。
「読め」
ファイルを男に突き返した。男はもう抵抗することを諦めたようだった。ファイルを開いて読み始めた。
男の言葉は、―それはぼくの寝言であるわけだが― 何の意味も脈絡もなくただただ続いた。ぼくはそこに何も見いだすことができなかった。それは異国の全く知らない他人のおしゃべりのように、ぼくの耳を通り抜けていった。この男がこんなものになぜ興味をもつのか全くわからなかった。こんなことのために苦しみ抜いた数ヶ月が、間抜けで情けなく、そして腹立たしかった。
男が言葉を止めた。妙に悲しげな目で一瞬ぼくを見上げ、そしてまた読み始めた。
「○○○○○○○○○」
その瞬間、ぼくは雷に打たれたように倒れた。
気がついたら朝だった。ぼくは知らない公園に打ち捨てられていた。駅への近道なのだろう。スーツ姿の男たちがぼくの傍らを通り過ぎていく。誰もぼくのことなど気にかけはしない。
あの男があのとき何と言ったのか、覚えてはいなかった。ただ聞いてはいけない何かを聞いてしまったこと、そしてもう二度と、今までのような人生を生きることができないことを、明確に理解していた。
ぼくはゆっくりと立ち上がり、そして歩きだした。
|
| おわり |
|
|

| 西岡兄妹情報 |
|
仕事を辞めました。これから2ヶ月の長い休みに入ります。もちろん創作のためですが、今のところ焼酎を飲みながらテレビを見ております。
(西岡智) |
|