西岡智(西岡兄妹)
|

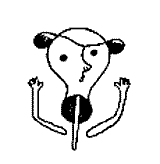 |
*短篇小説
「花の船」
第四回
イラスト/ 西岡千晶 |
|
|

どうやらぼくは走ってきたらしい。坂道を駆け下りてきたらしい。息が切れて喉の奥に痰が絡み付く。ふくらはぎの筋肉が勝手にびくびくと動いている。ぼくは道の真ん中で両膝に手をついて、その不自然な形を変に身体に力を入れて支えている。吐いた息が頬を伝って空に消えていく。錆色の厚い雲が空からぶら下がって陽の光を遮っている。今何時かもわからない。いやそれどころか、ぼくにはここがどこで、ぼくが誰なのかすら曖昧で、薄明の下ただ一人で混乱したまま動けないでいる。腋の下にかいた汗が、二の腕を伝って横腹を伝ってその冷たさにぞっとする。やけに湿気の多い不快な冬の日。
さてと、ぼくは大きな息をついて、そしてそれでもどこかで落ち着いていた。こういう状況をこれまで何度も経験してきたように。そう、どうやらぼくは走ってきたらしい。坂道を駆け下りてきたらしい。息が切れて喉の奥に痰が絡み付く。ふくらはぎの筋肉が勝手にびくびくと動いている。ぼくは道の真ん中で両膝に手をついて、その不自然な形を変に身体に力を入れて支えている。吐いた息が頬を伝って空に消えていく。錆色の厚い雲が空からぶら下がって陽の光を遮っている。今何時かもわからない。いやそれどころか、ぼくにはここがどこで、ぼくが誰なのがすら曖昧で、薄明の下ただ一人で混乱したまま動けないでいる。腋の下にかいた汗が、二の腕を伝って横腹を伝ってその冷たさにぞっとする。やけに湿気の多い不快な冬の日。べろりと剥がれる。記憶が逆流して意識と重なる。今を過去にすることで、その先の過去に繋げる。ちょっとした操作に過ぎぬ。そして過去の意識の無いところ未来は無い。錆色の厚い雲が空からぶら下がって陽の光を遮っている、やけに湿気の多い不快な冬の日。もう一度頭の中で繰り返す。
ゆっくりと膝から手を離し、何かを押し返すようにして背中を伸ばす。今は正月である。さっきから車の一台も通らないのはそのせいである。そしてこの休みを利用してぼくは久々に帰郷してきたのである。一人の女を連れて、たぶん両親に紹介するために。気恥ずかしさと、なぜか少しの罪の意識を感じていた。両親の少し困惑した顔が頭に浮かぶ。しかしそれ以上にぼくの変わってしまった体型が両親を驚かせた。ほんのここ数年の間に、ぼくの身体は醜く変貌していた。加齢のせいか酒のせいか、もしかしたら薬のせいやもしれぬ。腹の周りに巻き付いた脂肪がぼくの印象すら変えてしまっていた。ぼくは自分に一日一時間の歩行を課した。家を出てぼくは歩き出した。過去の日の通学路の記憶を巡って。学校まで片道三十分、往復一時間である。その散歩の途中にぼくはこうしてこの場所で動けなくなっていたのだ。何てことは無い、ちょっとした混乱に過ぎぬ。
一歩を踏み出す。この未来への行為が過去の中に霧散していく。確かに不思議な感覚ではある。ぼくは歩き出す。昔「蛇谷」と呼ばれた谷に架かる小さな橋を渡る。川は干上がっていて過ぎた時間の長さを知らせる。川の脇に寝そべるように耕された田圃は、打ち捨てられ背の高い冬枯れた草々に覆われている。森があり竹やぶがあり川があり、田圃が畑があり、それに寄り添うように人々の営みがあった。ぼくの子供の頃には連続性というか、ある種の必然性のようなものがそこにはあった。今はといえば、不自然なほど整然と立て並べられた宅地と、見捨てられ忘れ去られ野蛮さを感じるほどの無秩序な自然とが、鈍い刃物で切り裂かれている。この通学路で、この断絶した風景の中で今の子供たちは何を思う。そんなことをぼんやりと考えていた。橋から続く急な坂道を上る。思いの外足が軽い。さっきまで固まっていたのが嘘のようだ。息切れを起こす間もなく坂の上に立つ。風景が広がる。同じような区割りで立てられた同じような家々がずっと遠くまで立ち並び、その向こうに大きな工場群が薄く霞んでいる。急に、前方から後方から自転車に乗った人々の群れが、ぼくを挟むようにしてすれ違う。ふわりと飛ぶようにして彼らをよける。この町で一番大きな工場、N製作所の労働者たちだ。二十四時間稼働の工場の今は交代の時間なのだ。彼らは正月も無しに働いているのだ。疲れ果てた人々、その灰色の群れは饐えた息切れだけを残して見る間に景色の中に吸い込まれて消えていく。今も昔も変わらない、貧しい労働者たちの生活がそこにはあった。彼らの悲惨な人生を思って胸が痛くなる。
ぼくは歩き続ける。変わってしまった景色の中を、足の記憶だけを頼りにペースを崩さぬよう意識しながら。小さな商店がある。昔、子供たちが学校帰りに怪しげなお菓子や、合成着色料で舌に色の付くようなジュースを買ったあの店。シャッターが下りている。正月だから閉まっているのだろうか、いやそこはもうただの廃屋、人の営みも、子供たちの賑わいの痕跡すら感じられない。大体この町自体がそうだ。確かに人口は増えているはずなのに、人の気配が全くしないのだ。寒々しい風景。ぼくは歩いた。首筋から入った冷気が背中の辺りで固まる。
一つ小高い丘の前で足を止める。きっと宅地化には適さなかったのだろう、そこだけは昔の面影を残していた。この丘を、春になると桜の木が屋根のように覆うこの坂を上ると小学校がある。そしてぼくはとりあえずの目的を果たして帰路につくのだ。一気に駆け上がる。学校が無い。以前ここに学校があった痕すら見つけることができなかった。そこには古い小さな墓地がぽつり忘れられていた。風化と苔で名前すら判読できない墓石が一個また一個とただ孤立している。花を手向ける人も無いこの墓地、こんな場所をぼくは見たことが無かった。四方を見渡す。この場所を頂点にして、家々が、町が垂れ下がるようにして広がっている。この風景をぼくは知らない。急に、言いようの無い不安、あるいは焦燥、そんな感覚がこみ上げてくる。食道のあたりに痛みを覚えて胸を押さえる。ぼくの記憶の不確かさ、ぼくの意識の不確かさ、そしてそれはぼくの存在の不確かさだった。ぼくは震えた。けっぷが喉を上がってくる。音をたてて飲み込む。ぼくがぼくではなくなっていくその何ともいえない感覚がぼくの腹の中に澱のように溜まっていくのを感じていた。慌てて今きた道を駆け下りる。でももう手遅れだということはわかっていた。
放浪者は見知らぬ家々の間を縫うようにして歩いた。歩くことにもう意味が無いことを彼は知っていた。ただ歩くこと以外に何一つできる行為が無いというその意識の希薄さが、彼のその呆然とした表情の中に見て取れた。そう彼は途方に暮れているのだ。放浪者は全く関係の無い他所者として町中を歩いた。歩いて歩いて歩き続けた。彼の記憶を揺り動かすものはどこにも無かった。記憶の主体である彼自身あるのかどうか確証が無かったのだから。もうどのくらい歩いたのかもわからなくなっていた。彼の消えかけた自己意識は時間の感覚すら追い求めることを止めていた。今や彼は誰でも何者でもあることができなかった。死ぬというのはこういうことかもしれないな、目の前の霧を掴むようにして彼は考えた。
誰も遊ぶものもいないうら寂しい小さな公園があって、その周りを市営住宅の同じような建物が囲んでいる。その脇の私道を彼は歩いた。たぶん孤独な老人だけが今では住んでいるのだろう、ベランダに小さな花々を飾っている窓がある。そんなことも彼の瞬きすら忘れた開いた視界の片隅を通り過ぎていった。彼は歩いた。そしてその突き当たり、黒い板張りの朽ちかけたタオル工場の前で足を止めた。全く人の気配は無いが、かたんかたんと機械の作動している音が聞こえる。かたんかたんと。かたんかたん微かに響くその音に彼は耳を澄ましているように見えた。ぴいんと何に繋がっているかもしれぬ彼の消えかけた記憶の糸が張りつめた音をたてた。
ぼくは古いタオル工場の前に立っている。この工場を抜けると梨園がある。ぼくは何の確証ももたぬまま、細い細い記憶の糸に引っ張られるようにして、迷路のような工場の敷地を小走りで駆け抜ける。そして梨園はあった。ただ所有だけしか意味していないような、力なくペンキの剥げかけた柵の中に、実を落とし葉を落とした梨の木々が身を寄せ合うようにして立ち並んでいる。細い農道が奥へと導く。この梨園の向こうには土手があってその先には大きな川がある。ぼくはしっかりした足取りで、でも後ろから見たらたぶんよろよろと揺れながら、農道を進む。夏、ニーニー蝉の鳴き声、小さな抜け殻、ベロアの触感。記憶に似たぼんやりとした感覚がぼくに戻ってくる。ニーニー蝉など本当にいたのだろうか、ニーニーと鳴く小さな蝉、これもただ遠い日の幻想、作り上げられた怪しげな記憶に過ぎないのではないか、不安も一緒に頭をもたげてくる、生きているという感覚と一緒に。木々の間を歩く。果たして土手がある。ぼくは土手を駆け上る。眼下に大きな川。この梨園の向こうには土手があってその先には大きな川がある。繰り返す。ぼくは今までに無いほどの強い現実感をもってそこに立つ。現実とは記憶の反復に他ならない。
川が流れている。いや流れているというのとは違う。暗い錆色の絵の具で塗り込めたように、空を写し込んで澱んでいる。川に向かって土手を下りて行く。滑らないようにしっかりと足を踏ん張って。
川縁を歩く。大きな川だ、確かK川。向こう岸は靄に霞んで、数十メートル先で空と同化している。まるで池のように静かだ。枯れ草を踏みながらしばらく歩くと小さな船着きがあって、小さな船が一艘繋がれている。その中で腰の曲がった老人が一人、忙しげに立ち働いている。近づいて行く。看板があって、渡し船、大人二百円、子供百円。老人はぼくに気づいているのかいないのか、黙々と働き続けている。彼は小さな船の内側いっぱいに花を飾っているのだ。不思議な光景だった。思わず声をかける。
「じいさん、いったい何をしているんだい」そういえば家を出てから初めて人と話した。声が少し震える。
「見ての通りさぁ、花を飾っておるんじゃ」この地方独特のイントネーションで老人が答える。
「船は出してもらえるのかい」何の考えも無しに言葉が出る。
「わしは渡し船の船頭じゃ、客さえいればいつでも出すわな。でもちょっと待っとくれ、一仕事終えてからじゃ」そう言ってしゃあしゃあと笑った。
不思議な老人だった。こうして目の前で話しているというのに、全く顔の印象が定着しない。まるで街中で行き過ぎる何人もの見知らぬ他人のように、イメージが意識の上っ面をすり抜けていく。刻まれた深い皺だけが彼の存在を確証している。何だか危うい。
「じいさん、いったい何をしているんだい」もう一度聞く。
「見てのとおりさぁ、花を飾っておるんじゃ、それにしてもおかしな時代じゃ、冬だというのに春の花も夏の花もある、金さえ出せば何でも買える、おかしな時代じゃあ、狂った時代じゃあ」そう言ってまたしゃあしゃあと笑う。皺がただ引きつったようにしか見えない笑顔で。ぞっとした、確かに危うい。
「何のために」
「たどり着けなかった旅人たちの魂のために」
老人は軍手をぱんぱんとはたいて、その笑顔とも何ともつかない顔を向ける。
「さあ支度は終りじゃ、早く乗っとくれ」
「残念、そういえば俺は金を持ってきてなかったよ、渡りたいのはやまやまだけど」
「そんなことはどうでもええ、これはお前さんの船じゃ、お前さんだけの船じゃ、乗らないのなら空で出るまで、さあ早く乗っとくれ」
嫌も応も無かった。ぼくはそれ以外選択する余地がないかのように船に乗り込む。
ぎぃと櫓の軋む音がして船は滑るように出ていく。ぼくは飾られた花の中に惚けたように座っている。そしてぼんやりとした不安感。
「この船はどこにたどり着くんだい」
「そんなこたぁわからん、船の向くまま流れのなすままじゃ、こんな静かな池みたいな水面でもそのすぐ下じゃあ水が轟々と流れとる、こんな棒切れ一本じゃあ何ともできねえ、何ともならねえ」
冗談とも何ともとれず、ぼくはただ笑った。老人もつられてしゃあしゃあと笑う。もうどうしようもなかった。
「風が出てきやがった、お客さん身体を低くそう横んなって、この広い川の中じゃこんな小船は風向き一つ、木っ端のように右に行ったり左に行ったりじゃ」
そう言われると少し寒い。老人に言われるまま船底に横になる。色とりどりの花に埋もれて仰向けに寝る。確かに頭の下でごうごうと水の流れる音が聞こえる。花々の匂いが混ざって鼻をかすめる。それもまた心地いい。錆色の空はそれ自体重力をもってぼくの身体を軽く圧する。色々な感覚がやっと元に戻ったような奇妙な安堵感。目を閉じてそしてぼくはそのまま眠ってしまうことになる。ぎぃぎぃと櫓を漕ぐ音が遠くに聞こえる。この途方も無い川をただただ流れに任せて。
どのくらい眠っていたのだろう。気がついた時ぼくはもう花も無い船の中で丸くなっていた。寒さで身体ががくがくと震えている。節々が痛む。海だった。港には廃船になった船の残骸が所在無さげに浮かんでいる。岸壁で老人が枯れた花を一本一本とたき火の中に投げ入れている。岸壁をよじ上り老人に近づく。
「じいさん、いったい何をしているんだい」
「見ての通りさぁ。花を燃やしておるんじゃ」そう言ってまた一本花を焼べる。
「俺はどのくらい眠っていたのかな」
「知らん、遠い昔の話じゃ」
なぜか今では老人の顔をはっきりと意識できる。まるでモノクロ写真のようにしっかりとした輪郭線をもって。そこにいるのは年老いたただの普通の漁夫だった。
「海は死んじまった」誰に話すでもなく老人が言う。
「どうして、こんなきれいな海なのに」海は底が見えるほど透き通っている。小魚の姿も無く。
「海は死んじまった、もう魚もおらん、漁師もおらんくなった、わしも元々は漁師じゃ、魚さえ捕れりゃあ船頭などしとらん、どこに行くとも知れん渡し船の船頭なんぞ」そう言ってまた一本と花を焼べる。
「じいさん、いったい何をしているんだい」繰り返される。
「見ての通りさぁ、花を燃やしておるんじゃ」
「何のために」
「たどり着けなかった旅人たちの魂のために」
老人の言葉が終わらないうちにぼくは背を向け歩き始めた。海から家までは一本道だ。ぼくはずんずんと歩いた。港を抜け、見知った道をずんずんと、徐々に歩幅を広げて。
帰り道はあっという間だった。ぼくは実家の玄関の前に立っている。安い正月飾り、プラスチックのみかん。中に入ると暖かい。暖房とそして人の温かさ。耳と指先が痺れる。居間には兄と妹、そしてぼくの恋人である女が三人で座ってテレビを見ていた。正月用の下らないお笑い番組、誰も笑うでも無く。両親の姿は無い。ぼくは挨拶もせず、台所に行って冷蔵庫を開ける。ビールを一缶取り出して、一気に半分ほど飲む。鼻が痛い。居間に戻る、誰も何も言わない。妹が帰省土産に買ってきた揚げ饅頭を立て続けに三つ食べる。ビールで湿らせながら。兄が口を開く。
「豚だな、お前は、その姿を鏡に写してみればいい、お前は痩せると言って家を出たのではなかったか、それが帰ってくるなり何だ、お前は昔からそうだ、努力ということが全くできない、両親に対しても家族に対しても、お前に与えられたそれなりの才能に対してもだ、お前の堕落した生活はお前の身体だけではなくお前の精神にも脂肪を付けてしまったようだ、父さんも母さんもどうして顔を出さないかお前にわかるか、それは罪の意識を感じているからだ、お前のような人間を作り出してしまったことを詫びているんだ、恥じているんだ、社会に対しても、お前に対してもだ、父さんも母さんもまだお前に希望をもっている、お前の更正にだ、でもお前はもうだめだ、長男として言わせてもらう、お前はただ自分の目先の欲求を満たすことしか考えない醜い太った豚だ」
二の句が継げない。なぜ帰ってきた早々こんなことを言われなければならないのか、全くわからない。今度は妹がぼくとは決して目を合わせないようにして話し出す。
「あなたは自分が周りからどのように見られているのかまるで考えようとしない、あなたの自意識はまだ子供の時のまま全く成長しようとしない、確かに昔はあなたは良くできた、勉強もスポーツもね、わたしにとってあなたは少し誇りだった、でもね年が経てば人は変わっていくの、人の評価もね、あなたは昔の写真を見て悦に入っている単なる太った落伍者に過ぎない、そしてそれを変えようともしない、意識することすらしようとしない、どうしようもない太った落伍者」
声が震えて言葉を止める。妹が今にも泣き出すのではないかと恐れた。助けを求めるようにして女を見る。
「あなたは決して自分自身に向き合おうとしない、あなたの弱さにも、あなたの良いところや才能にさえね、あなたはあなたをあなたの名前を他人の中にだけに見ようとしているの、自分ではなく他人にね、あなたは他人の口からあなたの名前が出るのをいつも涎を垂らして待っているの、あなたの欲しいのは名声だけ、真実なんかじゃない、あなたがわたしに求めたのもそれだけなの、だからわたしに満足できないの、あなたは自分にもわたしにも真実に向き合うことができないからいつも空っぽで飢えているの、だからいつもあなたはあなたの名前を食べようとして無駄なことばかり続けている、徒労だけで一生を終えようとしているの、あなたのお腹に付いているのは脂肪じゃなくてあなたの名声の残骸、もう取り去ることのできないあなたの恥部」
女は真っ直ぐぼくを見据えている、その視線に耐えきれず目をそらす。ぼくは床を睨みつけたまま何も言えないでいる。身体が震えているのがわかる。怒りからか恥からか。ぼくはビールの缶を床に叩き付ける。そして家を飛び出す。
ぼくは走る、人気の無い道を。信号を右に曲がる。下り坂に差し掛かりスピードを速めて。何が何だかわからない、息が切れる。ぼくにはもう帰るところが無いことを正確に意識している。その意識を振り払うようにぼくは走り続ける。頭の中が白く霞んでいく。
こうしてぼくはたどり着けない旅を始める。
|
| おわり |
|
|

| 西岡兄妹情報 |
|
当然分かっているとは思いますが、この物語はフィクションです。登場する企業・団体・人物はすべて架空のものです。本当です。
(西岡智) |
|